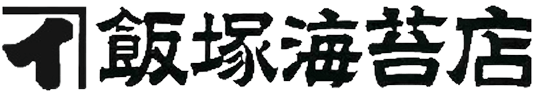陸採が始まる季節に ― 千葉各地の現場を歩いて
海苔づくりの始まりを告げる「陸上採苗(りくじょうさいびょう)」が、今年も各地で始まりました。
9月下旬から10月にかけて、木更津・富津・新富津・大佐和・行徳・船橋の6エリアを回り、
海苔師(のりし)の方々にお話を伺いながら、その現場を見学してきました。
どの地域にも、それぞれの工夫と想いがあり、千葉の海苔づくりの奥深さを改めて感じました。


木更津・金田 ― 水車が回る音の中で始まる海苔のサイクル
9月25日、最初に訪ねたのは木更津・金田。
斉藤隼人さんのグループでは、水車を3台回しながら、海苔の種付け作業が進んでいました。

水車で牡蠣殻についた胞子を網に付着させたのち、養生水槽(プール)に移して根をしっかり張らせます。

プールの中にはアサリをいれており、これは水質を保つための自然の清掃役。

こうした工夫ひとつにも、経験と知恵が詰まっています。
海苔の品種は生産者ごとに異なり、
水産公社の品種、九州から仕入れるもの、代々受け継がれてきた自家採取品種など実にさまざま。
公社品種は調子がよく、安定して胞子が放出されているそうです。
海苔づくりのスタートは、牡蠣殻に付着した胞子を温度管理し、
いかにタイミングよく放出させるかにかかっています。
この最初の工程を失敗すると、その年の生産に大きな影響が出るため、
各海苔師が慎重に行います。


富津 ― 品種へのこだわりと挑戦
10月2日には富津へ。スタートして2日目の現場で、松下真也さんのグループを訪ねました。

千葉の海苔師は、複数人でグループを組んで陸採を行うことが多く、
品種選びや管理方法など、互いに意見を交わしながら作業しています。


「ちばの輝き」はやや赤みがあるものの甘みが強く、
「エビス9号」は黒くて病気に強いが少し硬め、
「公社」系は平均点が高く安定感があり、
新しい「P241」は伸びにくいなど、それぞれの特性を理解した上で組み合わせて使う姿が印象的でした。
松下さんは特に味へのこだわりが強く、「従来品種でも十分に勝負できる」と話していたのが印象的でした。

富津では牡蠣を用いて水槽をきれいに保ち、
温度だけでなく風向きや天候を見極めながら微調整を行っていました。
今後は浮き流し養殖の網張りに移行し、支柱柵との併用で進めていくとのことです。
新富津 ― 圧巻のスケールと新しい品種への挑戦

10月6日、新富津では保坂さん、松下さん、平野さんらのグループに案内いただきました。

千葉県内でも屈指の生産量を誇るエリアで、陸上採苗の規模も圧倒的。
水車が一斉に回り、広がる網のプールの風景はまさに壮観でした。

今年は九州で人気の新品種にも挑戦しており、

来年は「P241」にも取り組む予定だそうです。
胞子をどの程度網につけるかは海苔師によって考え方が異なり、
環境や潮流に合わせて量を調整しているとのこと。
水車で付けた網は養生プールで約4時間休ませ、水を切ったのち冷凍庫へ。
この「冷凍網」は、後に海へ張り出す際に使用されます。
大佐和 ― 品種の使い分けと自然環境への期待
続いて訪れた大佐和では、平野さん・臼井さんからお話を伺いました。

このグループでは「福」と「9号」という2品種を使用。


「福」は高温に強く味が良い、「9号」は伸び足がよく収量が見込める品種です。
秋芽(あきめ)と呼ばれる初期収穫用の網は全体の2割ほどで、
それ以降は冷凍して保存し、二期作での生産に備えます。
最近は黒潮大蛇行の収束が報じられ、海の栄養状態が改善されることへの期待も語られました。
外洋水が入り込みすぎると栄養塩が薄まり、海苔の育ちに影響することがあるため、
漁師たちは日々、海況の変化に敏感に目を配っています。
行徳 ― 豊かな栄養塩が育む旨味
10月9日、行徳の後関さんを訪問。ちょうど採苗のスタート日でした。
行徳の海は栄養塩が豊富で、味の乗った海苔ができることで知られています。
ここでは三番瀬原藻から培養した種を使い、陸上採苗後は冷凍せず、
すぐに海に張り込みを行うという独自のスタイルです(※多くの地域では一度冷凍保管します)。
天候が荒れていたため、この日は翌日に作業を回したそうです。
行徳では支柱柵と浮き流しの両方式を併用し、
網の高さ調整や汚れ対策など、味と品質を左右する細やかな管理が行われています。
食害対策にも力を入れており、特にクロダイによる被害を防ぐため、
使わない網を“おとり”として海に出す工夫も成果を上げているとのことでした。
船橋 ― 雨の中でも着実に進む現場
10月11日は船橋へ。スタートして3日目、
松本さん・岩田さんに話を伺いました。
今年も「公社3号」「船橋原藻」「P241」を使用しており、
雨の中でも順調に胞子が放出されていました。
昨年は「P241」の生育に苦戦していましたが、今年は安定しているようです。
一時期、船橋市川沿岸では青潮の影響が懸念されていましたが、
今回は幸い大きな影響はなく、順調な滑り出しとなりました。
長年この地域の海を見続けてきた海苔師たちは、
「海の機嫌」を肌で感じながら、日々微調整を重ねています。
終わりに ― 一枚の海苔に込められた技と想い
陸上採苗は、海苔づくりの最初であり最も神経を使う工程です。
小さな胞子の放出タイミング、水温や風、天候、そして海の栄養状態。
どれひとつが欠けても、良い海苔は生まれません。
今回の視察で感じたのは、どの海苔師も自然と真摯に向き合い、
それぞれの方法で「最良の一枚」を追い求めているということ。
千葉の海苔づくりは、まさに人と海の共同作業です。